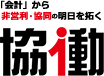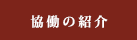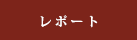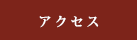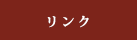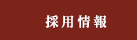事業譲渡時における中退共精算に係る留意点
Q:当法人は中小企業退職金共済事業(以下、「中退共」という)に加入していましたが、今年度途中において当法人の全事業を譲渡しました。中退共に係る契約については事業譲渡日と同日となるよう解約手続きをおこなっており、退職金共済契約解除通知書解約申請書も無事に受理されていました。
しかし、事業譲渡日後において中退共から被共済者である職員に支払われるものは、「退職金」ではなく、「解約手当金」であると説明を受けました。さらに「解約手当金」は、税法上も退職所得ではなく、「一時所得」として取り扱うとのことでした。「一時所得」となってしまうと税金が発生する可能性が高くとなると聞きましたので、「退職所得」として受け取ることはできないのでしょうか。
A:退職金共済契約解約申請書も受理されていますので、この時点での「解約手当金」からの「退職金」への変更は難しいでしょう。
今回のケースでは、事業譲渡日をもって被共済者である職員の退職手続きを先行しておこなう必要があったといえます。
【解説】
事業譲渡をおこなう場合、中退共に加入している事業者同士であれば中退共に係る契約の事業譲渡先法人への移管が可能となりますが、事業譲渡先法人は一定規模の法人であることが多く中退共の加入要件を満たさないことが多くなると想定されます(合併など他の組織再編も同様)。この場合、事業譲渡元法人が加入している中退共に係る契約は事業譲渡により引き継ぎができず、事業譲渡元法人において中退共に係る契約を精算することが求められます。
今回のケースにおける精算の方法として、中退共に対して「退職金共済契約解除通知書解約申請書」を最初に提出するのではなく「被共済者退職届」の提出をまずおこない、被共済者である全職員の退職手続きが完了したところで、「退職金共済契約解除通知書解約申請書」を提出し、契約の解除をおこなうべきであったといえます。
なお、中退共から支給される「退職金」、「解約手当金」のいずれについても、受け取る権利は本人に限定されており、退職金の受け取る権利を他の法人に譲渡したりすることができません。したがって、事業譲渡先法人への中退共に係る退職金権利の移行は認められず、中退共に係る契約の精算は事業譲渡元法人のほうでおこなうことになるのです。
それでは次に「退職所得」と「一時所得」にどれだけの税金負荷の差があるのかみていきます。
<税負担の比較>
・前提条件
一職員を比較対象とする。
退職金(解約手当金):6,000,000円
勤続年数:20年
(1) 退職所得
退職所得は、勤続年数に応じて毎年40万円の退職所得控除が認められている。
6,000,000円-(400,000円×20年)=△2,000,000円
マイナスとなるため退職所得は生じず、所得税は課されない。
(2) 一時所得
一時所得は、特別控除額500,000円と税率を乗じる前に1/2することが認められている。
(6,000,000円-500,0000円)×1/2=2,750,000円(一時所得)
これに税率を乗じて所得税を求めることになる。
2,750,000円×10%-97,500円=177,500円(所得税額)
退職所得と一時所得では「所得税」だけで比較しても、一時所得では177,500円もの税負担を強いられることが分かります。今回は計算していませんが、住民税も社会保険料の負担も発生することになるので、実際の負担はさらに増加することになります。
今回のケースであれば、本来支払う必要のない税金を負担することがないよう、事前に中退共と直接やり取りするなどし、きちんと「退職金」として支給されるよう手続きをおこなっておく必要がありました。
このほかに中退共では、「退職金」「解約手当金」の額の算定方法は、掛金月額と納付月数に応じて算定されるのは同じですが、掛金助成を受けた者の解約手当金の額は一定減額されることになります。また、一時所得は総合課税として給与の金額と合算して申告することになるので「解約手当金」で受け取ると所得税率も「退職金」として受け取る場合に比べて高くなります。
事業譲渡等組織再編に係る取引は想定外の出来ことが多々起こります。今回のケースのように取り返しがつかない(税負担を免れることができない)ことも起こります。こうした点からも、スケジューリングの策定および想定される課題等をできる限り早い時期に認識をしておき、不明、不安な点等があればそれぞれの機関や専門家などに問い合わせをおこない解決してくことが非常に重要となってきます。
以上