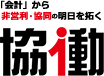1.概要
公益法人制度は、2008年12月に施行され、2013年11月に旧制度からの移行期間が終了し、本格的な運用がはじまって、早や8年が経過したところである。この間、公益認定等委員会の下で公益法人の会計に関する研究会が開催され、「公益法人の会計に関する諸課題の検討」がなされ、一定の見直し検討がされたものの、収支相償基準については、会計理論上の根本的な矛盾が存在し、かつ、実務上、当該基準が桎梏となるケースもあり得るため、再検討(もしくは、個別の事情を勘案して総合的に判断するという視点)が必要であるとの見解を示すものである。
2.収支相償基準とは
収支相償とは、公益目的事業について、「事業に係る収入はその事業に要する適正な費用を償う額を超えない」(公益認定法5条6号)とするものであり、換言すれば収支トントンということである。
公益法人の公益目的事業に係る収入が、公益目的事業の適正費用を超えないことが基準とされ、収支相償については、基本的に二段階で判断する。第一段階では、公益目的事業単位で事業関連収入と費用を比較する。第二段階では、第一段階の収入及び費用を含め公益目的事業を経理する会計全体の収入及び費用を比較する。但し、公益目的事業が一本(単一)である場合には、第一段階の判定は省略し、第二段階の判定のみ行う。
3.収支相償の計算(判定)
収支相償の計算においては、原則として事業年度毎に収支が均衡することが求められるが、そもそも事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立った事業運営が求められるため、ある事業年度で収入過剰になった(剰余金が発生した)場合でも、公益目的事業拡充等に充てるための特定費用準備資金として計画的に積み立てる等で、中長期的に収支が均衡することが確認されれば、収支相償の基準は充たすものと判断される。
また、剰余金が発生した場合でも、短期的に(翌々事業年度までに)解消される見込みがあるものであれば、収支相償の基準を充たすものとして弾力的に取り扱うことも可能とされている。実践的には、剰余金が生じた理由及び当該剰余金を短期的に解消する具体的な計画を説明することになる。なお、FAQV-2-(5)には、剰余金が発生した場合に必要な措置として、以下の4つが列挙されている。
(1)公益目的保有財産に係る資産取得資金への繰入
(2)当期の公益目的保有財産の取得
(3)翌事業年度における剰余金の解消についての説明
(4)その他、個別の事情についての説明
4.個別の事情について
上述の(4)その他、個別の事情については、各公益法人の特殊事情や事業概況及び経営状況を総合的に勘案して、事業継続に支障が出ることがないよう柔軟に判断されるべきと考えるが、FAQV-2-(5)の但書には、「基本的に、過去に生じた赤字の補てん、借入金の返済等については、剰余金の解消方策として認められません。」とあり、この記載が実務上の障害になりかねない。以下に事例を挙げながら問題点等を説明をする。
5.事例1
そもそも、収支相償は正味財産増減計算書を基に計算し、損益上の均衡であり資金繰り上の均衡ではないため、減価償却費などの非資金費用の自己金融効果(減価償却費などの非資金費用は支出を伴わない費用であり、資金の流出がなくその分だけ手元に資金が残る効果のこと)だけでは、借入金の返済が賄えず、資金繰りが悪化するケースがあり、公益法人の存続基盤が危ぶまれる可能性がありうる。
例えば、公益目的事業用設備や建物の取得を借入金で対応する場合、下記の事例のように借入期間を耐用年数ではなく現実的な返済期間にすると、収支相償を遵守すれば資金繰りが困難となり経営破たんしかねない。このように設備投資を行った場合には、収支計算と損益計算には乖離が生じその乖離を埋めるためには、借入返済原資相当の剰余金が必要となるのである。したがって、設備投資に関する借入金の返済原資として、剰余金を充てれるようにしない限り事業が継続できなくなる可能性があり、少なくとも設備投資に関する借入金の返済については、剰余金の解消方策として柔軟に認めるべきであると考える。
(事例)公益目的事業に必要な建物(病院)を銀行借入で取得した
|
建物の取得価額
|
39億円
|
|
借入金額
|
39億円
|
|
建物の耐用年数
|
39年
|
|
毎年の減価償却費
|
1億円
|
|
毎年の収入
|
1億円
|
|
減価償却費以外に事業費は発生しないと仮定
|
(耐用年数に見合った返済期間にした場合:非現実的)
|
借入金の返済期間
|
39年
|
|
|
毎年の返済額
|
1億円
|
|
正味財産増減計算書
|
資金繰り表
|
|
収入
|
1
|
収入
|
1
|
|
減価償却費
|
-1
|
借入金返済
|
-1
|
|
|
0
|
|
0
|
|
収支相償OK
|
資金繰りOK
|
(現実的な返済期間にした場合)
|
借入金の返済期間
|
20年
|
|
|
毎年の返済額
|
1.95億円
|
|
正味財産増減計算書
|
資金繰り表
|
|
収入
|
1
|
収入
|
1
|
|
減価償却費
|
-1
|
借入金返済
|
-1.95
|
|
|
0
|
|
-0.95
|
|
収支相償OK
|
資金繰りNG
|
(収入を増やさない限り資金繰りが成り立たない)
|
借入金の返済期間
|
20年
|
|
|
毎年の返済額
|
1.95億円
|
|
毎年の収入(増額)
|
1.95億円
|
|
正味財産増減計算書
|
資金繰り表
|
|
収入
|
1.95
|
収入
|
1.95
|
|
減価償却費
|
-1
|
借入金返済
|
-1.95
|
|
|
0.95
|
|
0
|
|
収支相償?
|
資金繰りOK
|
↓
収入超過にして剰余金を出し、借入金の返済に充てる必要がある
6.事例2
剰余金が発生した翌年度(あるいは翌々年度)に損失が発生する見込みがある場合には、適切な説明を施したうえで、剰余金を繰り越すことが認められている。すなわち、黒字が先に出て後で赤字が出る場合には、赤字の補てんが容認されているのである。他方、赤字が先に出て後で黒字が出る場合には、過去の赤字の補てんは認めないとされている。同じ赤字の補てんであり、中期的に収支相償を充たしているのであれば、後先関係なく認めるべきであり、過去の赤字の補てんは認めないとするのは、論理薄弱である。
例えば、新規の公益目的事業を起こす際には、開業初年度に開業費や定率法による減価償却費等の費用負担が重く、経営的には徐々に軌道に乗ってくるのが常であり、このようなケースでは、赤字が先行して発生し、後年の黒字で埋め合わせするものである。したがって、過去の赤字の補てんを認めないとするのは、補助金行政に頼らず、自前で公益目的事業を拡大させようとする自助努力に逆行するものであり、公益法人制度改革の趣旨に沿っていない規定といえる。
事業の継続性や事業の性質に鑑みれば、収支相償の判断は中期的に継続して判断すべきであり、少なくとも公益認定後に生じた過去の赤字については、翌年度以降の剰余で補填できるようにすべきであると考える。
7.まとめ
公益認定等ガイドラインでは、「事業の性質上特に必要がある場合には、個別の事情について案件毎に判断する」とされており、FAQにおいて具体的な方策を例示しているが、事例検討したように、FAQの「基本的に、過去に生じた赤字の補てん、借入金の返済等については、剰余金の解消方策として認められません。」を形式的に捉えるのは適切ではなく、あくまでも「個別の事情」を総合的に勘案して判断されるべきである。
したがって、公益法人が公益目的事業の実践、発展に資するうえで、収支相償要件の形式的なあてはめが事業上の桎梏にならないよう配慮されるべきであり、また、公益法人のほうでは、損益と収支(資金繰り)のタイムラグの矛盾【事例1のケース】や中期的な視点で収支相償を判断すべき点【事例2のケース】を論理的かつ具体的に説明することが求められる。
公認会計士 田中淑寛
|