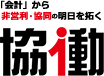レポート > 財務・会計
特定費用準備資金は収支相償の解消に使用できるか?
1.はじめに
内閣府公益認定等委員会は、公益法人制度の運用の一環として、委員会の下に公益法人の会計に関する研究会を設けて、実務上生じている種々の課題について検討を行っている。平成29年度報告では、より多くの公益法人が特定費用準備資金の活用の促進を図ることを目的に、(1)特定費用準備資金の要件を明確化し、(2)従来認められていなかった新たな特定費用準備資金の計上方法を認めている。
しかし、特定費用準備資金はそもそも使い勝手が良くなく、今回のように特定費用準備資金の弾力化を図ったところで、収支相償の根本的な解決策にはならない。収支相償基準は公益法人が継続的に事業を遂行する以上は、中長期的に収支が均衡することを担保できるように理論構成すべきものである。
以下に、特定費用準備資金の性質を解説し、現行の公益法人制度における収支相償基準の問題点及び改善提案を行う。
2.特定費用準備資金とは
特定費用準備資金とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために、法人の任意で積み立てる資金のことである。積立の5要件は、(1)資金の目的である活動を行うことが見込まれること、(2)資金の目的毎に他の資金と明確に区分して管理され、貸借対照表の特定資産に計上していること、(3)資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取崩すことができないものであること又は目的外で取崩す場合に理事会の決議を要するなど特別の手続が定められていること、(4)積立限度額が合理的に算定されていること、(5)特別の手続の定め、積立限度額、その算定根拠について事業報告に準じた備置き、閲覧等の措置が講じられていること、である。
具体例としては、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用などが考えられる。
3.資産取得資金とは
特定費用準備資金に類似する概念として、資産取得資金がある。資産取得資金とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用いる実物資産を取得又は改良するために積み立てる資金のことである。積立要件は、(1)と(4)が異なり(2)(3)(5)は特定費用準備資金と同じである((1)資金の目的である財産を取得し又は改良することが見込まれること、(4)当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額が合理的に算定されていること)。
具体例としては、建物や設備等の取得のための積立資金、減価償却引当資金(いわゆる更新投資のための積立)などが考えられる。しかし、資産取得資金は、収支相償の第一段階(個別公益目的事業での収支相償)においては使用できず、公益目的事業が複数ある場合には、まず、収支相償の第一段階において収入が費用を上回る場合には、その事業に係る特定費用準備資金への積立額として整理せざるを得ないのである。
4.特定費用準備資金の使い勝手の悪さ
特定費用準備資金への積立は、会計上、貸借対照表上の取引(損益が発生しない取引)であり、収支相償や公益目的事業比率といった認定基準においては、積立額を費用とみなして取扱うことになっている(いわゆる「みなし費用」)。
そして、積立額を取崩す場合には、積立の反対で、費用の減算(繰入収益)とみなして取扱われ、収支相償の計算上プラス要因となるのである。すなわち、特定費用準備資金は一時的にみなし費用として収支相償の計算上マイナス要因とすることが可能であるが、短期間の間に(最長5年あるいは10年)積立額を取崩す必要があり、その際には繰入収益(みなし費用のマイナス)を計上しなければならず、収支相償の短期的なタイムラグの調整にしか利用できず、使い勝手が悪いといえる。特定費用準備資金の利用だけでは、根本的な収支相償の課題解決にはつながらないのである。
他方、収益事業等からの利益額の繰入が50%の場合(50%超の場合はダメ)において、資産取得資金の積立は収支相償の計算上マイナス要因として使え、かつ取崩の際には特定費用準備資金とは異なり、みなし費用のマイナスにはならないため、収支相償の計算上プラス要因とはならない利点がある。但し、下記の事例のような施設系の事業を行っている公益法人にとっては、資産取得資金を使用したとしても収支相償基準の制度的矛盾が残るのである。
5.収支相償基準の制度的矛盾
病院等の施設運営を公益目的事業として経営する公益法人においては、医療水準を維持、発展させるために多額の設備投資が必要とされるケースが少なくない。多額の設備投資に際して、設備(建設)資金を金融機関等から借入調達した場合、減価償却費の推移と借入返済額の推移に乖離が生じうる。つまり、(1)定率法で減価償却費を計上している場合には、当初段階で「減価償却費>借入返済額」(減価償却費は逓減のため)となり得るし、定額法で減価償却費を計上している場合には、当初段階で「減価償却費<借入返済額」(一般的には借入金の返済期間は建物や医療機器等の有形固定資産の耐用年数よりも短いため)となり得る。
そもそも、収支相償は正味財産増減計算書を基に計算し、損益上の均衡であり資金繰り上の均衡ではないため、減価償却費などの非資金費用の自己金融効果(減価償却費などの非資金費用は支出を伴わない費用であり、資金の流出がなくその分だけ手元に資金が残る効果のこと)だけでは、借入金の返済が賄えず、資金繰りが悪化するケース((2)の場合)があり、公益法人の存続基盤が危ぶまれる可能性がありうる。したがって、設備投資に関する借入金の返済原資として、剰余金を充当(一定の黒字が必要ということ)できるようにしない限り事業が継続できなくなる可能性があり、少なくとも設備投資に関する借入金の返済については、剰余金の解消方策として柔軟に認めるべきであると考える。
また、(1)の場合、赤字が先行して発生し、後年の黒字で過年度の赤字を埋め合わせするものである。したがって、過去の赤字の補てんを認めないとするのは、補助金行政に頼らず、自前で公益目的事業を拡大させようとする公益法人の自助努力に逆行するものであり、公益法人制度改革の趣旨に沿っていない規定といえる。事業の継続性や事業の性質に鑑みれば、収支相償の判断は中長期的に継続して判断すべきであり、少なくとも公益認定後に生じた過年度の赤字については、翌年度以降の剰余で補填できるようにすべきであると考える。
6.まとめ
平成29年度報告にある特定費用準備資金の検討は、小手先の対処療法であり、収支相償基準の根本的矛盾の解決にはならない。
公益認定等ガイドラインでは、「事業の性質上特に必要がある場合には、個別の事情について案件毎に判断する」とされているにもかかわらず、FAQの「基本的に、過去に生じた赤字の補てん、借入金の返済等については、剰余金の解消方策として認められません。」が桎梏となっている。当該FAQは見直し(削除)されるべきであり、収支相償要件は、「個別の事情」を総合的に勘案して判断されるべきである。
(公認会計士 田中淑寛)