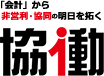レポート > 税 務
いわゆる「節税保険」に対する規制の動向
法人向けの保険商品で、いわゆる「節税保険」と呼ばれるものがあります。一定の生命保険契約等について、その支払った保険料の1/2あるいは全額が損金になることにより、保険契約期間中の法人税負担が少なくなるというものです。もちろん法人税が少なくなったとしても、単に保険料を支払っているだけでは法人側にメリットはありません。こうした保険商品は中途解約することが前提にされており、解約時の返戻率8割超など相当高く設定された解約返戻金を受け取ることで、「節税」効果と資産形成を享受できるというのが生命保険会社の触れ込みです。こうした「節税保険」の推定市場規模は契約保険料ベースで8~9千億円といわれており、保険市場の3割にも達しているそうです。
2019年2月に、大手生命保険会社の多くが「節税保険」商品の販売を休止しました。これは、国税庁がこうした「節税保険」の根拠とされている「法人税通達」の改定を検討していることを受けたものであり、特にターゲットにされたのは、「法人税個別通達」の穴を突いたような全額損金算入をうたう保険商品であり、ここ近年、大手生命保険会社による販売競争が過熱してきたことを問題視し、規制を強化しようというものです。
1.非営利・協同経営体における「節税保険」活用の注意点
こうした「節税保険」について、非営利・協同の経営体でもまれに活用しているケースを見受けますが、適切に内容を理解することが重要です。これらの保険商品は「節税」とうたっていますが、あくまで「課税の繰り延べ」に過ぎません。なぜなら、保険料を支払っている契約期間中は確かに一定額が損金になるため法人税負担は少なくなりますが、将来的に解約した際の解約返戻金はその年度の益金となるので、通算した課税所得は基本的に変わりません。保険会社は、「解約年度に役員退職金など多額の損金発生が見込まれれば相殺されて課税されない」といったセールス・トークで商品を勧めてきますが、そもそも解約返戻金がなければ、役員退職金などにより当該年度の法人税負担は少なくなる(仮に、当該年度の課税所得がマイナスになっても繰越欠損金は10年間繰り越せる)わけですから、やはり事業が継続される限りは課税を繰り延べているに過ぎません。むしろ解約返戻率が100%を割り込んでいるのであれば、通算で考えても資金的には必ず減少している点を正確に理解すべきです。
また、これも「節税保険」に加入している法人等でまれに見受けられますが、経営的に非常に厳しいため多額の赤字が生じており、そもそも法人税など発生していないケースです。こうした経営体では「節税効果」は全くなく、当該保険契約はマイナスでしかありません。さらに、ただでさえ厳しい経営状態であるにも関わらず資金も流出していきます。即刻、契約内容の見直しや解約を進めることが適当です。
こうした点を正しく認識したうえで、当面の税負担を軽減しながら、役員退職金など将来の多額な資金負担に備えて資産形成をおこなうということであれば、こうした保険商品を活用することも考えられなくはないですが、保険会社が一生懸命売り込む理由(すなわち、「保険会社が儲かる仕組み」ということ)を考えれば、加入者側にはそれほどメリットのあるものではないことは明らかです。
基本的に将来に渡って継続することが前提の「確定給付型企業年金」などと比べれば、「節税保険」は一定融通が利くことは間違いありませんが、決して保険会社に勧められるままに加入することのないよう、各法人の中長期的な経営見通しをもったうえで意思決定していくことが望まれます。
2.退職金に関する「会計」と「税」の乖離
そもそも、このような「節税保険」が過熱する根本的な要因は、退職金に関する「会計」と「税」の乖離が拡大していることが影響しています。
過去には退職金期末要支給額の一定部分につき税務上も損金として認められていた時期もありましたが、2002年度の法人税法改定により退職給付引当金は全額損金否認とされました。したがって、企業年金に加入して掛金を支払うなど実際の資金支出がない限り、退職給付引当金繰入額などの退職給付費用は一切損金とはなりません。一方で、労働の対価として職員に支払う退職給付債務は毎期発生しているため、真実の経営実態を把握するためには、会計上は多額の法人税負担をおこないながら、退職給付引当金を適切に計上しなければならないという矛盾が生じます。(なお、退職金を職員に支払った際には損金になりますので、中長期的にみれば、退職給付引当金を計上すること=法人税を多く負担するということではありません。「節税保険」が課税の繰り延べであることの反対で、税金の前払いのようなイメージですが、納税者側に不利であることは明らかです。)
日本の退職金制度は、先ほども述べたとおり、労働の対価として賃金の後払い的性格であることは明確であり、合理的な費用計上は税務上も損金として認められて当然です。特に、営利を目的としていない非営利・協同の経営体にとっては、重たい税金負担は事業存続の可否に直結しかねません。税務当局が、保険会社が儲けるための過度な「節税保険」に対する規制を強めることは結構ですが、根本的にはこうした「会計」と「税」の乖離を見直していくことが重要であり、そうでなければ税務当局と保険会社の「いたちごっこ」は続くのではないでしょうか。
(千葉 啓)