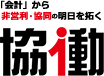憲法のもとでの源泉徴収制度について考えてみる
講演会の講師に支払う交通費等に関する源泉徴収に関連して、憲法のもとでの源泉徴収制度について雑記しようと思う。用語を含めて考察したものではないことを予めお詫びしておく。
非営利・協同の組織等では、法人税も消費税も申告納税する必要がない場合が多いが、源泉所得税の税務調査を受けることがある。法人登記をしていない労働組合や人格のない社団等も税務上は基本的に法人とみなされて源泉徴収の義務を負わされているからである。
調査官の指摘として「講師に支払った報酬については源泉徴収されているが、講師に支払った交通費についての源泉徴収がされていない」という指摘に出くわすことがある。
講師に立て替えてもらった交通費の実費を、領収書等も確認してキチンと清算しているのに、なぜ源泉徴収義務違反などと言われなければならないのか、という話しである。
各論の前に、憲法のもとでの源泉徴収制度の位置づけを少し考えてみる。
憲法の原則は「自主的申告納税制度」である。源泉徴収制度は、徴税の効率性・確実性の観点から、原則を補完する制度と説明されている。
源泉徴収の実務が厄介なのは、国(税務署)と法人(源泉徴収義務者)と個人(本来の所得税の納税義務者)の3者が登場して、その真ん中に法人が置かれるからである。法律関係上は、税務署と法人の間には税法上の債権債務関係があり、個人と法人の間には民法上の債権債務関係があるという構造として整理されているそうだ。ポイントは所得税のうち、源泉徴収制度の範囲に入るものについては、個人と税務署との間に、直接の税法上の関係が無いということである。(個人は流動性が高く、捕捉しにくいから、法人を使って支払った時点で捕捉させるという発想だろう)
そのため、源泉徴収の誤りを正す場合には、法人が個人と税務署の間に入らなければならず、法人は源泉所得税の本税の追加納付の他に、不納付加算税と延滞税といったペナルティーまで被ることになる。(大変な実務を負わされて費用弁償さえ無いのに)
「自主的申告納税制度」という憲法の原則において、本来的には負わされる必要の無い税法上の義務を、徴税の効率性・確実性の観点から法人に負わせる理屈は、国の税務実務を分かち合って効率的に運営することが、公共の福祉に反しない限りにおいて(すなわち基本的人権を侵害しない範囲で)のみ成立するものと思われる。従って、憲法の原則を補完する制度として源泉徴収制度が容認されるのは、法人にとって過度な負担や不合理にならない必要最小限度の「判定しやすい」範囲でのみ容認されると考えるべきだろう。
源泉徴収の対象は「限定列挙」なので、これに該当するかどうかを法人が判定しなければならないが、世の中のサービスは複雑化多様化しており一概に判定できない場合も多くなっている。会社だと思ってしまう「屋号」も多いし、外国人(非居住者)のビルオーナー等も増えている。現状の源泉徴収の対象範囲は広すぎ、かつ判定しにくくなっていると思われ、徴税の効率性・確実性の確保に傾斜し過ぎていると思われる。対象範囲の絞り込みを含めて法人が「判定しやすい」仕組に修正する必要があろう。また、源泉徴収の判定を誤った場合でも、悪意の無い場合には、法人を介さず個人(本来の納税者)の確定申告において調整できる仕組に修正する必要もあろう。
前置きが長くなったが、講師の交通費を実費精算した場合でも、支払った交通費は源泉徴収の対象という通達の話しに移ろう。
講師への報酬は源泉して支払って、交通費や宿泊費は領収書を受け取って実費精算しているという場合が多いと思われる。経済的な実質が立替金の清算であり、適当かつ当然だと思っている。
しかし、所得税の基本通達204-2では交通費・宿泊費を報酬に含めて源泉せよ、ということになっている。これは、講師の側の事業所得(或いは雑所得)の計算上の基本原則として、収入も支出も、それぞれ全額を計上しなければならず相殺してはダメということがあり、その原則に基づいて報酬も交通費・宿泊費も収入だから、区分して支払っていても全部合計したところで源泉せよという理屈である。例外として、法人が直接交通機関やホテルに支払ったものは、講師としては自分で払ってないから正確な収入と支出の金額を認識できないので、法人が直接交通機関やホテルに支払った部分は源泉徴収の対象にしなくて良い(204-4)ということになっている。
個人税務の基本原則を持ち出しているが、現実の問題意識は、講師が交通費名目で利ざやを取っているかも知れないから、或いは、収入に計上しないのに経費にだけ計上しているかもしれない、といったことのようだ。現場の調査官からもこういった説明を聞く。
また、例外の例外みたいな話しもある。講演会場の最寄り駅から現地までのタクシー代については、講師が支払った領収書と引換に清算した場合は、法人の職員がお出迎えをしてタクシーに支払ったものとして源泉徴収しなくて良いとされているようだ。客観性・信憑性が高いという判断だろう。業界紙の税務通信(No3395)の記事がネタ元だが、税務調査等の現場ではそういう対応が多いのだろうと思う。
しかし、客観性・信憑性という点では、非営利・協同の組織等の皆さんが行っている実費精算も十分だろうと思われる。講師が買った最寄り駅までの鉄道会社の領収書(或いは経路を確認してWEBで鉄道料金を確認した結果)と、先ほどのタクシーの領収書と、本質的に何が違うのだろうか。
「所得税基本通達逐条解説」によれば、弁護士が依頼人である法人から受ける旅費等について源泉徴収の対象とすることを相当とする判決が東京高裁で出ていることが紹介されているが、昭和49年の判決である。駅の券売機で領収書も出ないし、WEBでチェックもできないし、旅館も手書きの領収書の時代の判決である。
非営利・協同の組織等を含めて多くの法人が、交通費等について厳密に実費精算をするのは、組織運営や財政の健全性と透明性を担保するといった構成員・関係者の要請であるとともに、社会的にも企業モラルとして要請されるからであろう。同時に、実費精算を曖昧にすれば、それこそ税務上は、経済的利益の供与などとして不利益を被ることが想定されるからであろう。
つまり、当たり前のこととして実費精算が原則とされ、清算して処理完了であるのに、報酬料金の支払いについてだけは異なる対応をするということは、実際問題として現場感覚に馴染まず、実行に困難性を伴うものと思われる。更に言えば、講演の請負契約に係る交通費等と、顧問契約の遂行に係る交通費では取り扱いが異なると思われる。顧問契約は請負でなく委任契約(又は準委任契約)である。委任業務を遂行するために必要な経費は委任した法人の負担に帰属するのが筋であり、顧問の個人所得の必要経費に帰属しないものと思われ、源泉徴収は不要だと思われる。ますますもって訳が分からず、実行困難だと思われる。
前置きで雑記したように、源泉徴収制度は法人にとって過度な負担や不合理にならない必要最小限度の「判定しやすい」範囲でのみ容認されるべきで、実行に困難性を伴う運用は適当では無いだろう。客観的に事実確認ができる領収書等によって実費精算している場合には、支払者が直接支払った場合(基本通達204-4)に準じて、源泉徴収しなくて差し支えないといった運用を緩和する通達が入るべきだと思っている。
この論点は、非営利・協同の組織等の税務調査でたびたび登場する。調査官のなかには、実情にそぐわない矛盾を理解していて、「領収書もキチンとあるし、チェックもしてあるので、指導事項にしましょう」といった対応もある。それでも、修正額が年間10万を超えると「どうしようかな」と悩む印象を受ける。通達は公務員にとっては法律なので悩むのだろう。現場の調査官にとっても緩和通達が望まれよう。
長期にわたって税務調査に付き合っていられないから、やむを得ず修正に応じることも多いと思われる。その後の源泉徴収実務も従前どおりの実費精算を継続する判断であれば、不本意である旨をキチンと表明して(できれば意見書などで主張して)回答を得てから修正に応じるといった対応が好ましいだろう。税務署の調書資料に不本意であることを残すためである。そうしておかないと、次の税務調査において、前回の「了解」事項なのに改善が見られないという理解につながりかねないからだ。
雑記の最後に少しだけ毒を吐いておこう。平和憲法を内閣の解釈で「戦争ができる」ことにして「戦争法」を強行成立させる政治状況である。源泉徴収制度はもともと戦費調達の徴税制度で、その後スクスク育てられ範囲が拡大されてきたということを忘れたくない。徴税の効率性・確実性のために、憲法の原則を制限して、国民の「負担とリスク」を押しつけるという意味で、マイナンバー制度も根が同じだと思う。「国旗国歌法」も思い出したい。国会審議では内心の自由は保障され義務づけも強制もしないと総理大臣が答弁していたが、国歌斉唱に不起立の教員の減給処分を裁判所までが是認し、今や国立大学やアスリートにまで強制が及びつつある。法律に明記されない「歯止め」など「歯止め」にはなりえず、時の権力者の判断で際限なく拡大される恐怖を感じる。自民党は憲法改正草案で「公共の福祉」⇒「公益及び公の秩序」に変質させていることも重大だ。「私を含むみんなのため」⇒「権力者が定める国益のため」に基本的人権を制限できるという考えになれば、源泉徴収制度も無制限に拡張され「キケン」な仕組みに変貌しよう。
岡本 治好