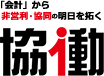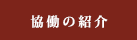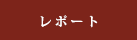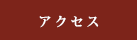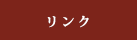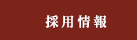レポート > レポート
医療生協の発行する領収書に印紙の貼付は必要か
1. 印紙税の課される領収書
印紙税法上、「売上代金の受取書」(領収書)は記載金額が5万円以上の場合200円の印紙税がかかるとされています。また、「営業に関しない受取書」については印紙税が課されない旨もあわせて記載されています(印紙税法「別表第一」より)。
「営業」に関する5万円以上の売上代金の受取書には印紙が必要で、「営業」に関しない受取書には不要ということです。では「営業」とは何かというと、これは国税庁の質疑応答事例に示されています。そこでは、「営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含む」と定義されています(国税庁 質疑応答事例「営業の意義」)。
医療生協は消費生活協同組合法(以下「生協法」)に基づき設立され、医療や福祉に関する事業を主たる事業とする「会社以外の法人」であり、営利法人や公益法人に該当しない、いわゆる印紙税法上の「中間法人」です。したがって、①利益または剰余金の配当又は分配をすることができる医療生協が②出資者以外の第三者に対しておこなう事業は営業となり、5万円以上の領収書を発行する場合印紙の貼付が必要となるということです。
2. この間の判例の紹介
2023年3月8日(一審)および2023年10月18日(二審)、上記①の条件の考え方と、②の「出資者」の範囲に関する新たな判例が示されました。原告はG生活協同組合、被告は国で、印紙税の過怠税の賦課決定処分の是非が争われた裁判(※)です。その判決のポイントは以下の通りです。
(1) 明確になった「出資者」の範囲(家族組合員の取扱い)
②の条件である「出資者以外の第三者」に組合員の家族を含むのかという点は長年「グレーゾーン」であり、本裁判の争点の一つでもありました。これまで国税当局は出資者の範囲につき、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」(生協法第16条)という規定に基づき、実際に出資を行った組合員に限ることとしていました。しかし判決は、同じく生協法の定める「定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。」(同第12条2項)という規定を理由に、家族組合員に対する領収書も営業に該当しないと判断しました。これにより原告の組合員家族に対する領収書への課税は取消となりました。これまでグレーだった組合員家族の利用が員外利用に該当しないとされたことは画期的な判決です。この判決を受けて国税庁は「消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて」を24年6月に発出し、家族組合員に対する領収書を申告対象としていた場合、一定の条件のもとに還付請求が可能であるということを明らかにしています。
(2) 「営業」に該当するかの判断基準
原告はまた、医療生協がおこなう医療福祉等事業についても印紙の貼付は不要であるという主張を展開しました。その主な理由は、原告は専ら医療福祉等事業しか営んでいないところ、生協法51条の2第2項により、(医療福祉等事業により生じた)「積立金は医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては取り崩してはならない」とされているため、法的に剰余の割戻しができない、というものです。つまり生協法上、医療福祉事業における剰余金の配当は認められていないため、専ら医療福祉等事業しか営まない医療生協は上記①の条件を満たさない、という主張です。
しかしこの主張は次のような理由で認められませんでした。まず、原告の定款には、「剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる」と明記されていました。また、確かに医療福祉等事業は法的に剰余の配当が認められませんが、同じく原告の定款には医療福祉等事業以外の事業(例えば「組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業」や「組合員及び組合職員の、組合事業に関する知識の向上を図るために必要な教育をおこない、及び情報を提供する事業」等)を行うことが記されていました。これらの事業は法的には剰余金の配当が禁じられていません。定款に剰余金の配当が「できる」と記載されており、また医療福祉等事業以外の事業を行うことを定款に明記していたため、医療福祉等事業も含めて「営業」と見做すべきだ、という判断です。事業の内容が営利であるか非営利であるかを問わず、定款上で配当が「できる」法人であれば出資者以外に対する事業は「営業」であり、5万円以上の領収書は印紙税の課税対象となることが示されたのです。
この結論は控訴審においても覆えらず、一審と同様、法令又は定款の定めにより剰余金の配当ができないこととなっている場合には印紙税は非課税となるが、そうでなければ一般的に課税、という見解が示されています。
その他、原告生協は地裁で「定款77条は死文(作成ミスの削除漏れ)」との主張をしましたが認められませんでした。また、高裁でも区分経理を含めて医療福祉等事業は配当不可であり、医療福祉等事業以外の事業を行っていても医療福祉等事業は非課税との主張や、医師個人・医療法人との矛盾を憲法14条(法の下の平等)違反とする主張も展開しましたが、これらも認められていません。
3. 本件に関する当職の見解
私たちのクライアントのいくつかの医療生協に個別に訊ねてみると、剰余金の割戻し(出資配当)が「できる」法人、「できない」法人、規定がない法人と様々でした。消費生協の模範定款では剰余金の割戻しは「できる」になっており、これをそのまま援用している場合には「できる」規定になっているようです。
では「定款上出資配当『できない』としていれば、医療生協の事業は『営業』に該当しないのか」と問われれば、これはまだ明確な結論が出ておらずここではっきりと申し上げることはできません。しかし、仮に税務調査等において指摘された場合には「できない」規定になっている旨をきちんと説明すべきでしょう。
また、そもそも論として、生協にとって組合員の利用を追求するのは、生協の設立目的・法的性質・運営理念の全てにおいて根幹をなす要素です。生協としての健全な運営・発展のためには組合員の利用の促進が不可欠であり、入院や外来、健康診断等の生協の事業を組合員以外の方が利用した場合には、生協の理念を広め、組合員になってもらうことを呼びかけるべきです。日常的にこうした実践を行っているのであれば、「生協の事業の利用者は基本的には組合員(その家族を含む)である」という主張も考えられるでしょう。
5万円以上の領収書1枚につき200円の印紙税ですから、金額的な影響は必ずしも大きくありません。会計窓口でその都度組合員かそうでないかを確認して印紙を貼付する手間や、その準備・管理に必要なコスト等も考慮しつつ、事業所での対応を法人として協議・検討しておくことが適切です。
※税務訴訟資料 第273号(順号13825)「印紙税過怠税賦課処分取消請求事件」
同 第273号(順号13893)「印紙税過怠税賦課処分取消請求控訴事件」
以上