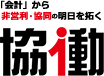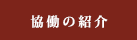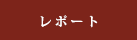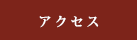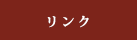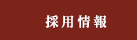新「公益法人会計基準」の検討すべき課題
1.はじめに
公益認定法の改正により、令和7年(2025年)4月1日から新公益法人法が施行され、同時に、新「公益法人会計基準」も施行されます(なお、会計基準については3年間の猶予規定が設けられています)。今回の制度改革は、現行の公益法人制度及び一般法人制度が創設された2006年度改革以来の2度目の改革となります。
今改正を概括すれば、概ね公益法人の継続性や発展・拡大再生産性を念頭に入れた持続可能性が意識された改正であったといえ、拙稿「病院等医療機関を運営する公益法人における収支相償基準の検討課題」で述べた、中期的な収支相償判断及び過去の赤字の補填についての課題は、適切な手当てが施され一定理にかなった改正となっています。他方、公益法人の実務担当者にとっては、新「公益法人会計基準」への対応は作業負荷がかかる改正内容となっている点は見過ごせません。会計基準の周知徹底や実務整備を図る目的から3年間の猶予期間が設けられているのは、激変緩和のためといえます。
「公益法人会計基準の検討経過」(内閣府公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会)において、「今回の公益法人会計基準の見直しが、法令改正に伴う必要な措置に留まらず、振替処理の廃止など公益法人会計全体の前提となる仕組みの見直しを含むことについて、公益法人の会計実務に多大な影響を及ぼす見直しであり、より時間をかけて、法令改正に伴う必須のものと切り離して検討を行うべきではないか、といった意見もあった」「研究会は、引き続きの検討とされた事項への対応に留まらず、公益法人の新基準案等への移行状況を注視するとともに、会計基準をめぐる環境変化等も踏まえ、随時必要な見直しを行っていくことも含め、今後も継続的に検討を行っていく。」とされています。
そこで、下記において、新「公益法人会計基準」につき、検討すべき課題を挙げて、必要な見直しを求めていくための論点整理をしています。
2.検討すべき課題
①「重要なステークホルダー」とは
新「公益法人会計基準」の冒頭に、「Ⅰ 財務報告の目的」が掲げられ、その中で「公益法人の責務としての財務報告」が求められています。これは、公益認定法において「公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示など、運営の透明性の向上に努めなければならない」ことが定められており(法第3条の2)、法令に基づく公益法人の適正な運営の基盤となるものです。
ところで、「Ⅰ 財務報告の目的」の2項で、唐突に「重要なステークホルダー」なる定義がなされ、「公益法人には、資源提供者、債権者、受益者、従業員、ボランティア従事者、地域住民、行政庁といった多様なステークホルダーが存在する。このうち、特に、資源提供者(財産拠出者、寄付者、会員、補助金等の提供主体など)が、公益法人における組織目的を達成するための活動の基盤となる重要なステークホルダーとなる。」とあります。私が危惧するのは、資源提供者(資金を出したもの)を公益法人の重要なステークホルダーと位置付けていることです。このことは、株式会社における株主重視の経営を想起させるものであり、公益法人の目的である「民間の公益活動によって、公益の増進及び活力ある社会の実現に資する」ことからすれば非常に違和感のある規定といえます。したがって、公益法人の目的を誤解させないためにも、「このうち、特に、資源提供者(財産拠出者、寄付者、会員、補助金等の提供主体など)が、公益法人における組織目的を達成するための活動の基盤となる重要なステークホルダーとなる。」の規定は削除すべきと考えます。
また、「重要なステークホルダー」と位置付けたことにより、財務諸表における注記で寄付金や補助金についての開示が詳細に求められていますが、誰からどこからもらったのかが重要ではなく、資源提供者の意図に沿って適切に使用されたのかが、開示情報としては重要なファクターとなるはずです。このことも含め見直しが必要と考えます。
②財務規律適合性に係る明細
新「公益法人会計基準」の附属明細書において、財務規律適合性に係る明細を作成する旨の規定がされています。財務規律適合性とは、中期的収支均衡、公益目的事業比率、使途不特定財産額に関する数値及びその計算を示したものです。従来定期提出書類の別表A~Cで開示されていた内容です。
ところで、財務諸表における附属明細書は、貸借対照表及び活動計算書に係る事項を表示するものであり、本表を補足するものです。しかしながら財務規律適合性は、本表に記載された数値を補足するものや内訳詳細を示すものではなく、法律上、公益法人に課せられた財務要件に適合しているかを記載したものにすぎません。公益認定法で求められる財務規律適合性に関する情報について開示するならば、財務諸表である附属明細書ではなく、財務諸表の欄外である事業報告書等で行うべきであり、附属明細書の開示対象から財務規律適合性に係る明細を省くべきと考えます。
法人の財務状況と財務規律適合性の情報が一体的に開示されることは、情報の受け手にとっての便益となるということが、改正の主旨と説明されていますが、会計学的に理路整然と構築されている財務諸表の概念を反故にすることは許されません。
③貸借対照表の内訳表
公益認定法の改正により、新「公益法人会計基準」でも区分経理が適用され、貸借対照表の内訳表の作成が任意から強制に変更され、原則としてすべての公益法人は、貸借対照表の内訳表を注記として作成する必要があります。
ほとんどの公益法人においては、主として公益目的事業を行い、付随的に収益事業等を行っていることからすれば、使途不特定財産を除けばほとんどの財産は公益目的事業に帰属していると看做すことができます。また、法人会計は管理費相当の赤字が蓄積されていくことが想定されますので、とどのつまり他会計からの借入(穴埋め)が必要となります。このような公益法人の特性からすれば、貸借対照表の内訳表を作成し開示する意味合いはないといえ、ステークホルダーにとっても無益です。したがって、従来通り、貸借対照表の内訳表の作成は任意にすべきであり、貸借対照表の本表でなく注記にしたからといって許容できるものではありません。
3.まとめ
「公益法人会計基準」は内閣府公益認定等委員会が作成したものですが、上記に示した通り、論理矛盾や制度主旨からの逸脱と思しき点があると考えます。それゆえ、当事者である公益法人や実務家である公認会計士が、実践的に検討課題を突き付け、3年間の猶予期間中に新「公益法人会計基準」の発展的見直しを求めていく必要があります。私どもも積極的に意見発信していきたいと思います。
公認会計士 田中淑寛